問題51
囲碁の棋士、呉清源は____生まれの著名なプロである。
A. 日本
B. 中国
C. 韓国
D. 台湾
正解: B. 中国
説明: 呉清源は1914年に中国福建省で生まれ、日本で活躍した伝説的な棋士です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、呉清源が中国生まれで日本で有名なんて、囲碁が国境を越えてこんなすごい人を生んだのが感動的だなと思いました。
問題52
囲碁で、自分の石を強化する手筋は____と呼ばれる。
A. ハネ
B. ツケ
C. ノゾキ
D. オサエ
正解: D. オサエ
説明: オサエは相手の石を押さえ、自分の石を強化する基本的な手筋です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、オサエなんて手筋があるなんて、囲碁の強化がこんなにシンプルで効果的なんだなと思いました。
問題53
囲碁の国際大会で、日本、中国、韓国が参加する団体戦は____杯である。
A. 応昌期
B. 農心
C. LG
D. トヨタ
正解: B. 農心
説明: 農心杯は3カ国の代表が戦う団体戦で、韓国が主催します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、農心杯が3カ国で戦うなんて、囲碁の国際大会がこんなに熱いとは知らなかったです。
問題54
囲碁の盤上で、隅を囲う基本的な形は____である。
A. シマリ
B. ハサミ
C. ゲタ
D. シチョウ
正解: A. シマリ
説明: シマリは隅を効率的に囲う定石の一つです。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、シマリが隅の基本形なんて、囲碁の序盤がこんなに決まってるのが面白いなと思いました。
問題55
囲碁のルールで、対局終了時にダメを埋める段階は____と呼ばれる。
A. ヨセ
B. セメアイ
C. コウ
D. セキ
正解: A. ヨセ
説明: ヨセは終盤にダメを埋めて領域を確定させる段階です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ヨセが終盤の鍵なんて、囲碁の最後がこんなに丁寧に締めくくられるのがすごいなと思いました。
問題56
囲碁の歴史で、「本因坊」の称号を初めて名乗ったのは____である。
A. 本因坊算砂
B. 本因坊道策
C. 本因坊秀策
D. 本因坊丈和
正解: A. 本因坊算砂
説明: 本因坊算砂は江戸時代初期に本因坊家を興した初代です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、本因坊算砂が初代なんて、囲碁の歴史にこんな古い名前が残ってるのがカッコいいなと思いました。
問題57
囲碁で、相手の石を分断する手筋は____と呼ばれる。
A. キリ
B. ツケ
C. ハネ
D. ノゾキ
正解: A. キリ
説明: キリは相手の石の連絡を切断する重要な手筋です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、キリで分断するなんて、囲碁の攻撃がこんなに鋭いとは知らなかったです。
問題58
囲碁のプロ棋士養成機関である「院生」の制度を設けたのは____である。
A. 日本棋院
B. 関西棋院
C. 国際囲碁連盟
D. 囲碁協会
正解: A. 日本棋院
説明: 日本棋院は院生制度を通じて若手棋士を育成しています。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、院生なんて育成システムがあるなんて、囲碁のプロがこんなに計画的に育てられてるのがすごいなと思いました。
問題59
囲碁の「新布石」を実践し、革命を起こした棋士は____である。
A. 本因坊秀策
B. 呉清源
C. 藤沢秀行
D. 李昌鎬
正解: B. 呉清源
説明: 呉清源は1930年代に新布石を導入し、伝統的な戦術を覆しました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、呉清源が革命を起こしたなんて、囲碁にこんな大胆な人がいたのが感動的だなと思いました。
問題60
囲碁の盤上で、中央を占める戦略的な位置は____と呼ばれる。
A. 天元
B. 星
C. 三々
D. 小目
正解: A. 天元
説明: 天元は盤の中央(10-10)を指し、戦略的に重要な位置です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、天元が中央の名前なんて、囲碁の盤にこんな壮大な位置があるのが面白いなと思いました。
問題61
囲碁で、相手の石を取るための罠を仕掛ける手は____と呼ばれる。
A. ゲタ
B. シチョウ
C. サバキ
D. ハサミ
正解: A. ゲタ
説明: ゲタは四角く囲んで相手の石を確実に取る手法です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ゲタが罠の手なんて、囲碁にこんな確実な取り方があるのがすごいなと思いました。
問題62
囲碁のタイトル戦「名人戦」を主催するのは____である。
A. 朝日新聞社
B. 毎日新聞社
C. 読売新聞社
D. 日本経済新聞社
正解: A. 朝日新聞社
説明: 名人戦は朝日新聞社が主催する日本の主要タイトル戦です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、名人戦が朝日新聞社主催なんて、囲碁のタイトルがこんな大きなメディアと繋がってるのが驚きでした。
問題63
囲碁で、自分の石を軽く扱う技術は____と呼ばれる。
A. サバキ
B. ハネ
C. ツケ
D. ノゾキ
正解: A. サバキ
説明: サバキは石を軽快に動かし、形を整える技術です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、サバキが軽い扱いなんて、囲碁にこんな柔軟な技術があるのが面白いなと思いました。
問題64
囲碁の歴史で、「碁聖」と呼ばれた江戸時代の棋士は____である。
A. 本因坊道策
B. 本因坊秀策
C. 本因坊丈和
D. 安井算哲
正解: A. 本因坊道策
説明: 本因坊道策は卓越した棋力から「碁聖」と称されました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、碁聖なんて称号があるなんて、囲碁の歴史にこんな偉大な人がいたのがすごいなと思いました。
問題65
囲碁で、相手の石に密着して打つ手は____と呼ばれる。
A. ツケ
B. ハネ
C. ノゾキ
D. オサエ
正解: A. ツケ
説明: ツケは相手の石に隣接して打つ攻撃的な手筋です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ツケが密着攻撃なんて、囲碁にこんな積極的な手があるのが意外でした。
問題66
囲碁の国際大会「LG杯」を主催する国は____である。
A. 日本
B. 中国
C. 韓国
D. 台湾
正解: C. 韓国
説明: LG杯は韓国のLGグループがスポンサーの国際棋戦です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、LG杯が韓国主催なんて、囲碁の国際大会がこんなに韓国で盛んだとは知らなかったです。
問題67
囲碁で、盤の隅を占める基本的な定石は____である。
A. 小目
B. 天元
C. ハマ
D. セキ
正解: A. 小目
説明: 小目(5-4)は隅を効率的に占める定石の一つです。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、小目が隅の定石なんて、囲碁の基本がこんなに名前で決まってるのが面白いなと思いました。
問題68
囲碁の棋士、藤沢秀行は____のタイトルを多く獲得した。
A. 本因坊
B. 名人
C. 棋聖
D. 十段
正解: C. 棋聖
説明: 藤沢秀行は棋聖位を6期獲得し、20世紀の名棋士として知られています。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、藤沢秀行が棋聖を6回も取ったなんて、囲碁にこんなすごい人がいたのが驚きでした。
問題69
囲碁で、石が生きるための最小限の目は____である。
A. 1つ
B. 2つ
C. 3つ
D. 4つ
正解: B. 2つ
説明: 2つの目を持つ石の集団は、囲まれても生きられます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、2つで生きるなんて、囲碁の生き残りがこんなシンプルなルールで決まるのがすごいなと思いました。
問題70
囲碁の「ハサミ」はどのような局面で使うか?
A. 相手の石を挟む
B. 自分の石を強化
C. 領域を広げる
D. 石を分断
正解: A. 相手の石を挟む
説明: ハサミは相手の石を両側から挟んで攻撃する手筋です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ハサミが挟む手筋なんて、囲碁にこんな分かりやすい攻撃があるのが面白いなと思いました。
問題71
囲碁で、江戸時代に家元制度を確立した将軍は____である。
A. 徳川家康
B. 徳川秀忠
C. 徳川家光
D. 徳川吉宗
正解: A. 徳川家康
説明: 徳川家康は囲碁を奨励し、家元制度の基礎を築きました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、徳川家康が家元制度に関わったなんて、囲碁がこんな歴史的な人物と繋がってるのがすごいなと思いました。
問題72
囲碁の棋士、李昌鎬は____の出身である。
A. 日本
B. 中国
C. 韓国
D. 台湾
正解: C. 韓国
説明: 李昌鎬は韓国出身で、1990年代から2000年代に世界を席巻しました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、李昌鎬が韓国出身なんて、囲碁の世界にこんな強い人が韓国から出たのが驚きでした。
問題73
囲碁で、相手の石を覗く手筋は____と呼ばれる。
A. ノゾキ
B. ツケ
C. ハネ
D. オサエ
正解: A. ノゾキ
説明: ノゾキは相手の石の隙間を覗き、弱点を突く手です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ノゾキなんて手があるなんて、囲碁にこんな細かい技術があるのが面白いなと思いました。
問題74
囲碁の「王座戦」を主催するのは____である。
A. 日本経済新聞社
B. 朝日新聞社
C. 毎日新聞社
D. 読売新聞社
正解: A. 日本経済新聞社
説明: 王座戦は日本経済新聞社が主催するタイトル戦です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、王座戦が日経主催なんて、囲碁の大会がこんな経済的なメディアと関わってるのが意外でした。
問題75
囲碁で、盤の中央を最初に占めることは____と呼ばれる。
A. 天元打ち
B. 星打ち
C. 三々打ち
D. 小目打ち
正解: A. 天元打ち
説明: 天元打ちは盤の中央(10-10)に最初に石を置く大胆な戦略です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、天元打ちが中央スタートなんて、囲碁にこんな大胆な一手があるのがカッコいいなと思いました。
問題76
囲碁の「コミ」が導入された目的は何か?
A. 先手の不利を補う
B. 後手の不利を補う
C. 石の数を調整
D. 対局時間を短縮
正解: B. 後手の不利を補う
説明: コミは先手(黒)の有利さを調整し、後手(白)にハンデを与えます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、コミが後手を助けるなんて、囲碁の公平さがこんなに考えられてるのがすごいなと思いました。
問題77
囲碁の盤の線は何本ずつ交差するか?
A. 15本
B. 17本
C. 19本
D. 21本
正解: C. 19本
説明: 標準的な囲碁盤は縦横19本の線で構成されます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、19本が標準なんて、囲碁の盤がこんなに広い設計だとは知らなかったです。
問題78
囲碁で「死に石」となる条件は何か?
A. 目が1つしかない
B. 呼吸点がなくなる
C. 相手の石に隣接
D. 盤の隅にある
正解: B. 呼吸点がなくなる
説明: 呼吸点がなくなり、完全に囲まれると死に石となります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、呼吸点がなくなると死ぬなんて、囲碁の石がこんなに生き物みたいだとは思わなかったです。
問題79
囲碁の「本因坊戦」の初代タイトル保持者は誰か?
A. 本因坊秀策
B. 呉清源
C. 坂田栄男
D. 藤沢秀行
正解: C. 坂田栄男
説明: 坂田栄男は1941年に初代本因坊となりました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、坂田栄男が初代本因坊なんて、囲碁のタイトルにこんな歴史的な人がいるのがすごいなと思いました。
問題80
囲碁の「セメアイ」で勝つためには何が必要か?
A. 目が多い
B. ダメが多い
C. 石が多い
D. 呼吸点が多い
正解: B. ダメが多い
説明: セメアイではダメ(呼吸点)の数が勝敗を決めます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、セメアイがダメで決まるなんて、囲碁の勝負がこんな細かい点で決まるのが面白いなと思いました。
問題81
囲碁の「星」の位置はどこか?
A. 3-3
B. 4-4
C. 5-5
D. 6-6
正解: B. 4-4
説明: 星は4-4の交点で、序盤の定石に使われます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、星が4-4なんて、囲碁の序盤にこんな決まった位置があるのが意外でした。
問題82
囲碁で「十段」の称号を初めて獲得した棋士は誰か?
A. 呉清源
B. 坂田栄男
C. 藤沢秀行
D. 林海峰
正解: B. 坂田栄男
説明: 坂田栄男は1961年に初代十段となりました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、坂田栄男がまた出てきて十段も取ったなんて、囲碁にこんなすごい人がいたのが驚きでした。
問題83
囲碁の「碁笥」に収納されるものは何か?
A. 盤
B. 石
C. 棋譜
D. 時計
正解: B. 石
説明: 碁笥は囲碁の石を入れる容器です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、碁笥が石入れなんて、囲碁の道具にこんな専用の名前があるのが面白いなと思いました。
問題84
囲碁の「応昌期杯」の優勝賞金が最も高い国はどこか?
A. 日本
B. 中国
C. 韓国
D. 台湾
正解: D. 台湾
説明: 応昌期杯は台湾の実業家応昌期が創設し、高額賞金で知られています。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、台湾が賞金高いなんて、囲碁の大会にこんな意外な国が関わってるのが驚きでした。
問題85
囲碁で「生き石」となる条件は何か?
A. 目が1つ
B. 目が2つ以上
C. ダメが1つ
D. 相手の石に隣接
正解: B. 目が2つ以上
説明: 2つ以上の目を持つ石は生き石とされます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、生き石が2つの目で決まるなんて、囲碁のルールがこんなに明確だとは知らなかったです。
問題86
囲碁の「ハマ」の計算方法は何か?
A. 囲んだ領域
B. 取った石の数
C. 盤上の石の数
D. ダメの数
正解: B. 取った石の数
説明: ハマは取った相手の石の数を指し、得点に加算されます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ハマが取った石の数なんて、囲碁の得点にこんな直接的な要素があるのが面白いなと思いました。
問題87
囲碁の「ゲタ」を使う目的は何か?
A. 石を逃がす
B. 石を取る
C. 領域を広げる
D. 石を強化
正解: B. 石を取る
説明: ゲタは四角く囲んで相手の石を確実に取ります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ゲタが取るためなんて、囲碁にこんな確実な手があるのがすごいなと思いました。
問題88
囲碁の「棋聖」の称号を初めて獲得した棋士は誰か?
A. 藤沢秀行
B. 呉清源
C. 坂田栄男
D. 林海峰
正解: A. 藤沢秀行
説明: 藤沢秀行は1977年に初代棋聖となりました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、藤沢秀行が初代棋聖なんて、囲碁のタイトルにこんな人がいたのがカッコいいなと思いました。
問題89
囲碁の「ヨセ」で重要なのは何か?
A. 石を取ること
B. ダメを埋めること
C. コウを仕掛けること
D. セキを作ること
正解: B. ダメを埋めること
説明: ヨセではダメを埋めて領域を確定させます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ヨセがダメ埋めなんて、囲碁の終盤がこんなに細かい作業だとは知らなかったです。
問題90
囲碁の「新布石」を提唱した棋士の出身国はどこか?
A. 日本
B. 中国
C. 韓国
D. 台湾
正解: B. 中国
説明: 呉清源は中国出身で、新布石を日本で実践しました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、新布石が中国出身の呉清源からなんて、囲碁の革新がこんな国際的な背景にあるのがすごいなと思いました。
問題91
囲碁の「天元戦」を主催するのはどこか?
A. 朝日新聞社
B. 毎日新聞社
C. 読売新聞社
D. 日本経済新聞社
正解: C. 読売新聞社
説明: 天元戦は読売新聞社が主催するタイトル戦です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、天元戦が読売主催なんて、囲碁のタイトルがこんな大きな新聞社と関わってるのが驚きでした。
問題92
囲碁で「サバキ」を使う場面は何か?
A. 石を強化
B. 石を軽く扱う
C. 石を分断
D. 石を取る
正解: B. 石を軽く扱う
説明: サバキは石を軽快に動かし、形を整えます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、サバキが軽く扱う技術なんて、囲碁にこんな柔軟な考え方があるのが面白いなと思いました。
問題93
囲碁の「シチョウ」を破る方法は何か?
A. 石を追加
B. コウを仕掛ける
C. セキを作る
D. ダメを埋める
正解: A. 石を追加
説明: シチョウは追加の石で逃げ道を作れば破れます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、シチョウを破るのが石追加なんて、囲碁の防御がこんなに簡単で賢いとは知らなかったです。
問題94
囲碁の「名人戦」の初代タイトル保持者は誰か?
A. 呉清源
B. 藤沢秀行
C. 坂田栄男
D. 林海峰
正解: C. 坂田栄男
説明: 坂田栄男は1961年に初代名人となりました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、坂田栄男がまた出てきて名人まで取ったなんて、囲碁にこんなすごい人がいたのがすごいなと思いました。
問題95
囲碁の「コウ」のルールを破るとどうなるか?
A. 石が取られる
B. 手が無効になる
C. 領域が減る
D. 対局が終了
正解: B. 手が無効になる
説明: コウのルール違反は無効となり、別の手を打つ必要があります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、コウを破ると無効なんて、囲碁のルールがこんなに厳格だとは思わなかったです。
問題96
囲碁の「三々打ち」の目的は何か?
A. 中央を占める
B. 隅を確保
C. 石を取る
D. 領域を広げる
正解: B. 隅を確保
説明: 三々(3-3)は隅を効率的に囲う定石です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、三々打ちが隅を狙うなんて、囲碁の序盤がこんなに細かく決まってるのが面白いなと思いました。
問題97
囲碁の「王座」の称号を初めて獲得した棋士は誰か?
A. 坂田栄男
B. 呉清源
C. 藤沢秀行
D. 林海峰
正解: A. 坂田栄男
説明: 坂田栄男は1953年に初代王座となりました。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、坂田栄男が王座も取ったなんて、囲碁のタイトルをこんなに制覇した人がいるのが驚きでした。
問題98
囲碁の「死活問題」を解く目的は何か?
A. 石の配置を覚える
B. 石の生死を判断
C. 領域を計算
D. 対局を予測
正解: B. 石の生死を判断
説明: 死活問題は石の生き死にを判断する練習です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、死活問題が練習用なんて、囲碁にこんなトレーニングがあるのがすごいなと思いました。
問題99
囲碁の「セキ」の特徴は何か?
A. 石が取られる
B. 双方が生きる
C. コウが続く
D. 目がなくなる
正解: B. 双方が生きる
説明: セキは双方が生きて膠着する状況です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、セキが双方生きるなんて、囲碁にこんな平和な状況があるのが意外でした。
問題100
囲碁の「耳赤の局」で有名な棋士は誰か?
A. 本因坊秀策
B. 呉清源
C. 藤沢秀行
D. 李昌鎬
正解: A. 本因坊秀策
説明: 本因坊秀策の「耳赤の局」は1851年の名局で、妙手に相手が驚嘆したとされます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、耳赤の局が本因坊秀策の名局なんて、囲碁の歴史にこんなドラマチックな話があるのが感動的だなと思いました。

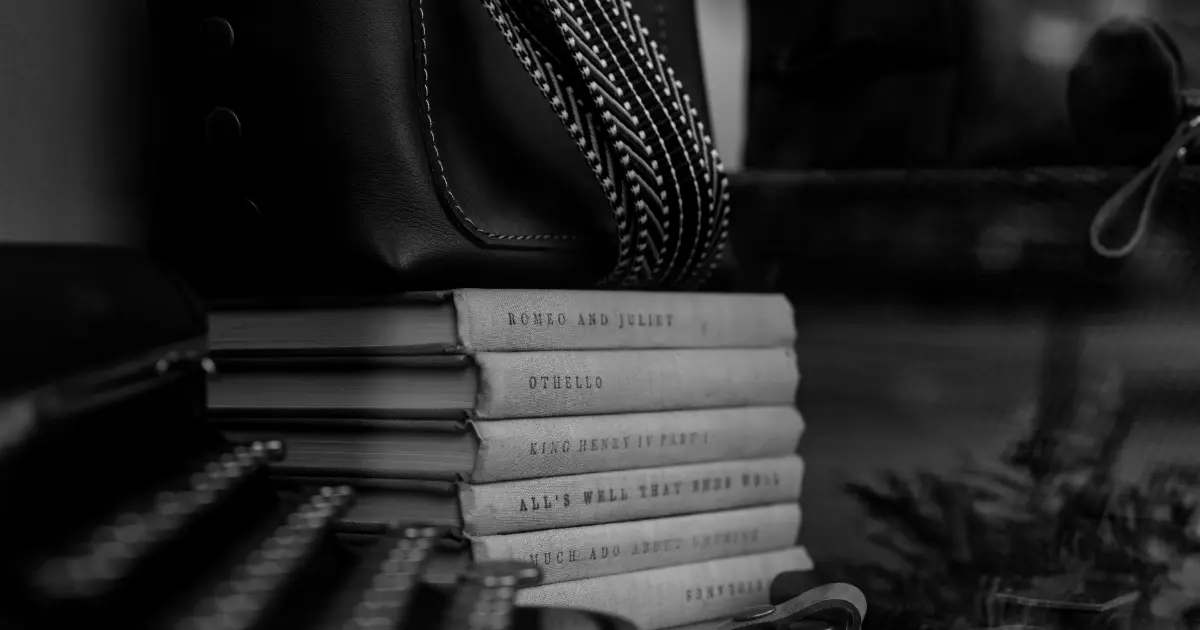



コメント