問題53
麻雀において、トップ目で点差が大きい場合に、守備的な戦術を取るべき状況は「______」と呼ばれます。
A. トップ目戦略
B. ラス目戦略
C. オーラス戦略
D. 押し引き
正解: A. トップ目戦略
説明: 「トップ目戦略」とは、トップ目で点差が大きい場合に、守備的な戦術を取ることでトップを守る戦略です。ラス目戦略は逆転を狙う戦略、オーラス戦略は最終局での戦略、押し引きは攻守の判断を指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、麻雀の戦略名が状況ごとにこんなに細かく分かれていることでした。特にトップ目とラス目で戦術が正反対になるのが面白いですね。
問題54
麻雀において、ラス目で点差を縮めるために、攻撃的な戦術を取るべき状況は「______」と呼ばれます。
A. トップ目戦略
B. ラス目戦略
C. オーラス戦略
D. 押し引き
正解: B. ラス目戦略
説明: 「ラス目戦略」とは、ラス目で点差を縮めるために、攻撃的な戦術を取ることで逆転を狙う戦略です。トップ目戦略は守備的な戦略、オーラス戦略は最終局での戦略、押し引きは攻守の判断を指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ラス目戦略の攻撃性がどれだけ逆転に特化しているかで、麻雀の駆け引きの深さを感じました。
問題55
麻雀において、最終局で点数状況に応じて適切な戦術を取るべき状況は「______」と呼ばれます。
A. トップ目戦略
B. ラス目戦略
C. オーラス戦略
D. 押し引き
正解: C. オーラス戦略
説明: 「オーラス戦略」とは、最終局(オーラス)で点数状況に応じて適切な戦術を取る戦略です。トップ目戦略はトップ目での戦略、ラス目戦略はラス目での戦略、押し引きは攻守の判断を指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、オーラスという言葉が麻雀特有の緊張感を表していて、ゲームのクライマックス感が伝わってくることでした。
問題56
麻雀において、トップ目で点差が小さい場合に、和了を重ねて点差を広げる戦術は「______」と呼ばれます。
A. トップ目戦略
B. ラス目戦略
C. オーラス戦略
D. 押し引き
正解: A. トップ目戦略
説明: 「トップ目戦略」とは、トップ目で点差が小さい場合に、和了を重ねて点差を広げることでトップを守る戦略です。ラス目戦略は逆転を狙う戦略、オーラス戦略は最終局での戦略、押し引きは攻守の判断を指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、トップ目でも点差次第で攻め方が変わる柔軟性が、麻雀の戦略にこんなに影響するとは思いませんでした。
問題57
麻雀において、ラス目で点差が大きい場合に、高い役を狙って逆転を図る戦術は「______」と呼ばれます。
A. トップ目戦略
B. ラス目戦略
C. オーラス戦略
D. 押し引き
正解: B. ラス目戦略
説明: 「ラス目戦略」とは、ラス目で点差が大きい場合に、高い役を狙って逆転を図る戦略です。トップ目戦略は守備的な戦略、オーラス戦略は最終局での戦略、押し引きは攻守の判断を指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ラス目がどれだけ大胆な賭けに出る必要があるかで、麻雀のドラマチックな展開が目に浮かびました。
問題58
あなたはトップ目で、点差が大きい状況です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 自分の手牌の点数を最大化する
正解: B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
説明: トップ目で点差が大きい場合、守備的な戦術が推奨されます。手牌を崩してでも安全牌を切る「ベタオリ」を選択することで、他家に振り込むリスクを最小限に抑え、トップを守ることができます。攻める選択肢(A, C)はリスクが高く、Dも状況次第では危険です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、トップ目でも攻めずに守る選択が正解になる状況がこんなに明確にあるなんて、麻雀の奥深さに感動しました。
問題59
あなたはラス目で、点差が大きい状況です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
説明: ラス目で点差を縮めるためには、攻撃的な戦術が必要です。低い点数の手牌でも、テンパイしている場合はリーチをかけることで和了の可能性を高め、逆転のチャンスを狙います。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ラス目だと低い点数でも攻めるのが正解と知って、麻雀のリスクテイクの度合いがすごいなと思いました。
問題60
あなたはオーラスで、2位と僅差のトップ目です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
正解: D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
説明: トップ目で点差が小さい場合、和了を重ねて点差を広げることが重要です。高い役を狙う(A)や攻撃的な行動(C)はリスクが高く、守備に徹する(B)も適切ではありません。低い点数の手牌でも和了を目指すことで、トップを守る可能性を高めます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、オーラスでの僅差の緊張感が、こんなにシンプルな選択にも影響を与えるなんて、麻雀の駆け引きがリアルに感じられました。
問題61
あなたはオーラスで、トップと僅差の2位です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 高い役を狙ってリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 高い役を狙ってリーチをかける
説明: 2位でトップと僅差の場合、逆転を狙うためには攻撃的な戦術が必要です。高い役を狙ってリーチをかけることで、トップを抜く可能性を高めます。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、2位でもトップを狙うためにこんなに大胆な行動が求められるなんて、麻雀の勝負所が熱いなと感じました。
問題62
あなたはオーラスで、ラス目ですがトップとの点差が小さいです。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
説明: ラス目でトップとの点差が小さい場合、攻撃的な戦術が必要です。低い点数の手牌でも、テンパイしている場合はリーチをかけることで和了の可能性を高め、逆転のチャンスを狙います。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、点差が小さいだけでラス目でも希望が持てる状況があって、麻雀の逆転劇がドラマみたいだなと思いました。
問題63
あなたはトップ目で、点差が小さい状況です。次のうち、最も危険な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
正解: A. 高い役を狙ってリーチをかける
説明: トップ目で点差が小さい場合、守備的な戦術が推奨されます。高い役を狙ってリーチをかけることはリスクが高く、他家に振り込む可能性があります。Bは守備的な行動、Cは状況次第、Dはトップを守るための適切な行動です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、トップ目でも油断できない状況があって、麻雀のバランス感覚がこんなに重要なんだと気づきました。
問題64
あなたはラス目で、点差が大きい状況です。次のうち、最も危険な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 高い役を狙ってリーチをかける
正解: A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
説明: ラス目で点差が大きい場合、攻撃的な戦術が必要です。手牌を崩してでも安全牌を切る「ベタオリ」は、逆転の可能性を完全に捨てることになり、最も危険な行動です。B, Dは攻撃的な行動、Cは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、守備が逆に危険になる状況があるなんて、麻雀の状況判断の難しさにびっくりしました。
問題65
あなたはオーラスで、3位ですがトップとの点差が小さいです。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
説明: 3位でトップとの点差が小さい場合、攻撃的な戦術が必要です。低い点数の手牌でも、テンパイしている場合はリーチをかけることで和了の可能性を高め、トップを狙います。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、3位からでもトップを狙えるチャンスがあって、麻雀の順位争いがこんなに熱いとは思いませんでした。
問題66
あなたはトップ目で、点差が大きい状況です。次のうち、最も危険な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
正解: A. 高い役を狙ってリーチをかける
説明: トップ目で点差が大きい場合、守備的な戦術が推奨されます。高い役を狙ってリーチをかけることはリスクが高く、他家に振り込む可能性があります。Bは守備的な行動、Cは状況次第、Dはトップを守るための適切な行動です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、点差が大きいのに攻めるのが危険なんて、麻雀の安全第一の考え方が意外でした。
問題67
あなたはオーラスで、2位ですがトップとの点差が大きいです。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 高い役を狙ってリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 高い役を狙ってリーチをかける
説明: 2位でトップとの点差が大きい場合、逆転を狙うためには攻撃的な戦術が必要です。高い役を狙ってリーチをかけることで、トップを抜く可能性を高めます。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、点差が大きいときの高得点狙いがこんなに重要で、麻雀の逆転のスリルがすごいなと思いました。
問題68
あなたはオーラスで、3位ですが2位との点差が小さいです。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
説明: 3位で2位との点差が小さい場合、順位を上げるためには攻撃的な戦術が必要です。低い点数の手牌でも、テンパイしている場合はリーチをかけることで和了の可能性を高め、2位を狙います。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、3位から2位を狙う微妙な点差の戦いが、麻雀の細かい駆け引きを際立たせていて面白いなと思いました。
問題69
あなたはトップ目で、点差が小さい状況です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
正解: D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
説明: トップ目で点差が小さい場合、和了を重ねて点差を広げることが重要です。高い役を狙う(A)や攻撃的な行動(C)はリスクが高く、守備に徹する(B)も適切ではありません。低い点数の手牌でも和了を目指すことで、トップを守る可能性を高めます。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、トップ目でも慎重に和了を重ねる姿勢が大事で、麻雀の堅実さが意外と光るなと感じました。
問題70
あなたはラス目で、点差が小さい状況です。次のうち、最も適切な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: B. 低い点数の手牌でもリーチをかける
説明: ラス目で点差が小さい場合、攻撃的な戦術が必要です。低い点数の手牌でも、テンパイしている場合はリーチをかけることで和了の可能性を高め、逆転のチャンスを狙います。守備的な行動(A, C)はトップ目や中位の場合に適しており、Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、点差が小さいだけでラス目がこんなに積極的に動けるなんて、麻雀の状況の変化が面白いなと思いました。
問題71
あなたはオーラスで、トップ目ですが2位との点差が小さいです。次のうち、最も危険な行動はどれですか?
A. 高い役を狙ってリーチをかける
B. 手牌を崩してでも安全牌を切る
C. 他家のリーチに対して積極的に攻める
D. 低い点数の手牌でも和了を目指す
正解: A. 高い役を狙ってリーチをかける
説明: トップ目で2位との点差が小さい場合、守備的な戦術が推奨されます。高い役を狙ってリーチをかけることはリスクが高く、他家に振り込む可能性があります。Bは守備的な行動、Cは状況次第、Dはトップを守るための適切な行動です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、オーラスでの僅差がこんなにプレッシャーを与えるなんて、麻雀の最終局面の緊張感がすごいなと思いました。
問題72
あなたはオーラスで、2位でトップと僅差です。次のうち、最も危険な行動はどれですか?
A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
B. 高い役を狙ってリーチをかける
C. 他家のリーチに対して守備に徹する
D. 役牌を鳴かずに手牌を進める
正解: A. 手牌を崩してでも安全牌を切る
説明: 2位でトップと僅差の場合、逆転を狙うためには攻撃的な戦術が必要です。手牌を崩してでも安全牌を切る「ベタオリ」は、逆転の可能性を完全に捨てることになり、最も危険な行動です。Bは適切な行動、C, Dは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、守備が逆転のチャンスを潰す危険な行動になるなんて、麻雀の攻めの重要性が際立っていて驚きました。
カテゴリ4: 特殊な戦術
問題73
麻雀において、役牌を鳴いて手牌を進める戦術は「______」と呼ばれます。
A. 鳴き戦術
B. 押し引き
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: A. 鳴き戦術
説明: 「鳴き戦術」とは、ポンやチーを活用して手牌を進める戦術です。特に役牌を鳴くことで手牌の進行速度を上げ、和了の可能性を vysokめます。押し引きは攻守のバランス、一発消しはリーチ後の一発目を防ぐ行動、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、鳴き戦術がこんなに明確な名前で定義されているなんて、麻雀の戦術の多様性がすごいなと思いました。
問題74
麻雀において、タンヤオを狙うために数牌の2~8のみで手牌を構成する戦術は「______」と呼ばれます。
A. 喰いタン
B. 押し引き
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: A. 喰いタン
説明: 「喰いタン」とは、タンヤオを狙うために数牌の2~8のみで手牌を構成し、鳴きを活用して和了を目指す戦術です。押し引きは攻守のバランス、一発消しはリーチ後の一発目を防ぐ行動、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、喰いタンという戦術がシンプルなのに効果的で、麻雀の役の作り方に工夫があるなと感じました。
問題75
麻雀において、役牌を鳴かずに手牌を進める戦術は「______」と呼ばれます。
A. 門前戦術
B. 押し引き
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: A. 門前戦術
説明: 「門前戦術」とは、鳴かずに手牌を進める戦術で、特にリーチやピンフなどの役を狙う場合に有効です。押し引きは攻守のバランス、一発消しはリーチ後の一発目を防ぐ行動、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、門前戦術がこんなに静かな戦略なのに強力で、麻雀の隠れた魅力があるなと思いました。
問題76
麻雀において、特定の牌を2枚待ちにして和了を目指す戦術は「______」と呼ばれます。
A. シャンポン待ち
B. 押し引き
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: A. シャンポン待ち
説明: 「シャンポン待ち」とは、特定の牌を2枚待ちにして和了を目指す戦術で、例えば3萬と5筒をそれぞれ1枚ずつ待つ形です。押し引きは攻守のバランス、一発消しはリーチ後の一発目を防ぐ行動、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、シャンポン待ちという名前がユニークで、麻雀の待ち方のバリエーションが豊富だなと思いました。
問題77
麻雀において、特定の牌を両面待ちにして和了を目指す戦術は「______」と呼ばれます。
A. リャンメン待ち
B. 押し引き
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: A. リャンメン待ち
説明: 「リャンメン待ち」とは、特定の牌を両面待ち(例:4萬5萬を持っていて3萬または6萬を待つ形)にして和了を目指す戦術です。両面待ちは待ち牌の枚数が多く、和了の可能性が高いです。押し引きは攻守のバランス、一発消しはリーチ後の一発目を防ぐ行動、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、リャンメン待ちがこんなに基本的なのに強力で、麻雀の待ちの戦略が奥深いなと感じました。
問題78
次のうち、鳴き戦術を最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
正解: B. ラス目で点差が大きい場合
説明: 鳴き戦術は手牌の進行速度を上げるため、ラス目で点差が大きい場合に最も有効です。トップ目(A)や僅差(C)の場合は守備的な戦術が推奨され、門前でテンパイ(D)の場合は鳴く必要がありません。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、鳴き戦術がラス目でこんなに活きるなんて、麻雀の状況ごとの使い分けがすごいなと思いました。
問題79
次のうち、喰いタンを狙う際に最も重要な要素はどれですか?
A. 役牌を鳴くこと
B. 数牌の2~8を優先的に集めること
C. 他家の捨て牌を読み取ること
D. 安全牌を確保すること
正解: B. 数牌の2~8を優先的に集めること
説明: 喰いタンを狙う場合、数牌の2~8のみで手牌を構成することが最も重要です。役牌(A)はタンヤオには不要であり、他家の捨て牌(C)や安全牌(D)も考慮されますが、まずは手牌の構成が基本です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、喰いタンがこんなにシンプルな条件で成り立つなんて、麻雀の役の作り方が意外と簡単だなと思いました。
問題80
次のうち、門前戦術を最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
正解: D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
説明: 門前戦術は、鳴かずに手牌を進める戦術で、特にリーチやピンフなどの役を狙う場合に有効です。自分の手牌が門前でテンパイしている場合、リーチをかけることで和了の可能性を高めます。A, B, Cは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、門前戦術がテンパイ時にこんなに輝くなんて、麻雀の静かな強さが印象的でした。
問題81
次のうち、シャンポン待ちを最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: B. 待ち牌の枚数が多い場合
説明: シャンポン待ちは、特定の牌を2枚待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合(A)は和了の可能性が低く、C, Dは守備的な状況であり、シャンポン待ちには適しません。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、シャンポン待ちが待ち牌の枚数にこんなに依存するなんて、麻雀の確率計算が大事だなと思いました。
問題82
次のうち、リャンメン待ちを最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: B. 待ち牌の枚数が多い場合
説明: リャンメン待ちは、特定の牌を両面待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合(A)は和了の可能性が低く、C, Dは守備的な状況であり、リャンメン待ちには適しません。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、リャンメン待ちがこんなに待ち牌の多さに左右されるなんて、麻雀の戦略の緻密さに驚きました。
問題83
次のうち、鳴き戦術を避けるべき状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
正解: D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
説明: 自分の手牌が門前でテンパイしている場合、鳴き戦術を避けるべきです。リーチをかけることで和了の可能性を高め、点数を最大化できます。A, B, Cは状況次第で鳴き戦術が有効な場合があります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、テンパイ時に鳴かない選択がこんなに大事なんて、麻雀のタイミングの重要性に気づきました。
問題84
次のうち、喰いタンを狙う際に最も危険な行動はどれですか?
A. 役牌を鳴くこと
B. 数牌の2~8を優先的に集めること
C. 端牌(1や9)を残すこと
D. 安全牌を確保すること
正解: C. 端牌(1や9)を残すこと
説明: 喰いタンを狙う場合、数牌の2~8のみで手牌を構成することが重要です。端牌(1や9)を残すことは、手牌の進行を遅らせ、和了の可能性を下げるため、最も危険な行動です。Aは状況次第、B, Dは適切な行動です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、端牌がこんなに邪魔になるなんて、麻雀の牌選びの厳しさに驚きました。
問題85
次のうち、門前戦術を避けるべき状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が鳴きでテンパイに近づく場合
正解: D. 自分の手牌が鳴きでテンパイに近づく場合
説明: 自分の手牌が鳴きでテンパイに近づく場合、門前戦術を避けるべきです。鳴きを活用することで和了の可能性を高め、逆転やトップを守るチャンスを増やせます。A, B, Cは状況次第で門前戦術が有効な場合があります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、鳴きが門前を上回る瞬間があるなんて、麻雀の柔軟な戦術に感心しました。
問題86
次のうち、シャンポン待ちを避けるべき状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: A. 待ち牌の枚数が少ない場合
説明: シャンポン待ちは、特定の牌を2枚待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合、和了の可能性が低く、シャンポン待ちを避けるべきです。Bは有効な状況、C, Dは守備的な状況です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、待ち牌の少なさがこんなにシャンポン待ちをダメにするなんて、麻雀の確率の影響が大きいなと思いました。
問題87
次のうち、リャンメン待ちを避けるべき状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: A. 待ち牌の枚数が少ない場合
説明: リャンメン待ちは、特定の牌を両面待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合、和了の可能性が低く、リャンメン待ちを避けるべきです。Bは有効な状況、C, Dは守備的な状況です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、リャンメン待ちも待ち牌次第で弱くなるなんて、麻雀の待ちの繊細さにびっくりしました。
問題88
次のうち、喰いタンを狙う際に最も危険な行動はどれですか?
A. 役牌を鳴くこと
B. 数牌の2~8を優先的に集めること
C. 字牌を残すこと
D. 安全牌を確保すること
正解: C. 字牌を残すこと
説明: 喰いタンを狙う場合、数牌の2~8のみで手牌を構成することが重要です。字牌を残すことは、手牌の進行を遅らせ、和了の可能性を下げるため、最も危険な行動です。Aは状況次第、B, Dは適切な行動です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、字牌が喰いタンでこんなに足枷になるなんて、麻雀の牌の選び方がシビアだなと感じました。
問題89
次のうち、門前戦術を最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
正解: D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
説明: 門前戦術は、鳴かずに手牌を進める戦術で、特にリーチやピンフなどの役を狙う場合に有効です。自分の手牌が門前でテンパイしている場合、リーチをかけることで和了の可能性を高めます。A, B, Cは状況次第です。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、門前戦術がテンパイ時にこんなに強いなんて、麻雀の静かな勝負所がカッコいいなと思いました。
問題90
次のうち、シャンポン待ちを最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: B. 待ち牌の枚数が多い場合
説明: シャンポン待ちは、特定の牌を2枚待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合(A)は和了の可能性が低く、C, Dは守備的な状況であり、シャンポン待ちには適しません。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、シャンポン待ちが待ち牌の多さにこんなに頼るなんて、麻雀の戦略のシンプルさに驚きました。
問題91
次のうち、リャンメン待ちを最も有効に活用できる状況はどれですか?
A. 待ち牌の枚数が少ない場合
B. 待ち牌の枚数が多い場合
C. 他家のリーチに対して守備に徹する場合
D. トップ目で点差が大きい場合
正解: B. 待ち牌の枚数が多い場合
説明: リャンメン待ちは、特定の牌を両面待ちにする戦術で、待ち牌の枚数が多い場合に有効です。待ち牌が少ない場合(A)は和了の可能性が低く、C, Dは守備的な状況であり、リャンメン待ちには適しません。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、リャンメン待ちがこんなに待ち牌の数に左右されるなんて、麻雀の確率の影響力がすごいなと思いました。
問題92
次のうち、鳴き戦術を避けるべき状況はどれですか?
A. トップ目で点差が大きい場合
B. ラス目で点差が大きい場合
C. オーラスでトップと僅差の場合
D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
正解: D. 自分の手牌が門前でテンパイしている場合
説明: 自分の手牌が門前でテンパイしている場合、鳴き戦術を避けるべきです。リーチをかけることで和了の可能性を高め、点数を最大化できます。A, B, Cは状況次第で鳴き戦術が有効な場合があります。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、鳴かない選択がこんなに大事な場面があるなんて、麻雀の戦略の幅広さに感動しました。
カテゴリ5: 状況判断
問題93
麻雀において、他家のリーチに対して、自分の手牌がテンパイに近い場合に攻撃を続ける判断は「______」と呼ばれます。
A. 牌効率
B. 読み
C. 押し引き
D. ベタオリ
正解: C. 押し引き
説明: 「押し引き」とは、攻撃を続けるか守備に回るかを判断する技術です。自分の手牌がテンパイに近く、和了の可能性が高い場合は、リーチに対して「押す」判断が適切です。牌効率は手牌の組み立て、読みは相手の手牌の推測、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、押し引きという言葉が麻雀の攻守の判断をこんなに的確に表しているなんて、用語のセンスに驚きました。
問題94
麻雀において、他家のリーチに対して、自分の手牌が弱い場合に安全牌を優先的に切る戦術は「______」と呼ばれます。
A. 牌効率
B. 読み
C. 押し引き
D. ベタオリ
正解: D. ベタオリ
説明: 「ベタオリ」とは、他家のリーチや危険な状況で完全に守りに徹し、安全牌を優先的に切る戦術です。牌効率は手牌の組み立て、読みは相手の手牌の推測、押し引きは攻守のバランスを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、ベタオリがこんなに守備に特化した戦術なんて、麻雀の安全重視の姿勢が面白いなと思いました。
問題95
麻雀において、リーチをかけた後、1巡目に出た牌を鳴いてリーチを解除する戦術は「______」と呼ばれます。
A. 牌効率
B. 読み
C. 一発消し
D. ベタオリ
正解: C. 一発消し
説明: 「一発消し」とは、リーチをかけた後、1巡目に出た牌を鳴いてリーチを解除する戦術です。これにより、他家の一発での和了を防ぎます。牌効率は手牌の組み立て、読みは相手の手牌の推測、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、一発消しという戦術がこんなにトリッキーで、麻雀の駆け引きがこんなに細かいとは思いませんでした。
問題96
麻雀において、他家のリーチに対して、自分の手牌がテンパイしている場合に、リーチをかける判断は「______」と呼ばれます。
A. 牌効率
B. 読み
C. 押し引き
D. ベタオリ
正解: C. 押し引き
説明: 「押し引き」とは、攻撃を続けるか守備に回るかを判断する技術です。自分の手牌がテンパイしている場合、他家のリーチに対してリーチをかける「押す」判断が適切な場合があります。牌効率は手牌の組み立て、読みは相手の手牌の推測、ベタオリは守備に徹することを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、押し引きがこんなに攻めの判断に直結するなんて、麻雀の勇気が試される瞬間だなと思いました。
問題97
麻雀において、他家のリーチに対して、自分の手牌がテンパイしているが待ち牌の枚数が少ない場合に、安全牌を優先的に切る戦術は「______」と呼ばれます。
A. 牌効率
B. 読み
C. 押し引き
D. ベタオリ
正解: D. ベタオリ
説明: 「ベタオリ」とは、他家のリーチや危険な状況で完全に守りに徹し、安全牌を優先的に切る戦術です。自分の手牌がテンパイしていても、待ち牌の枚数が少ない場合は和了の可能性が低いため、振り込みを防ぐことが優先されます。牌効率は手牌の組み立て、読みは相手の手牌の推測、押し引きは攻守のバランスを指します。
感想: このクイズを作っていて驚いた点は、テンパイでも守る選択があるなんて、麻雀の状況判断の難しさが際立っていてすごいなと思いました。


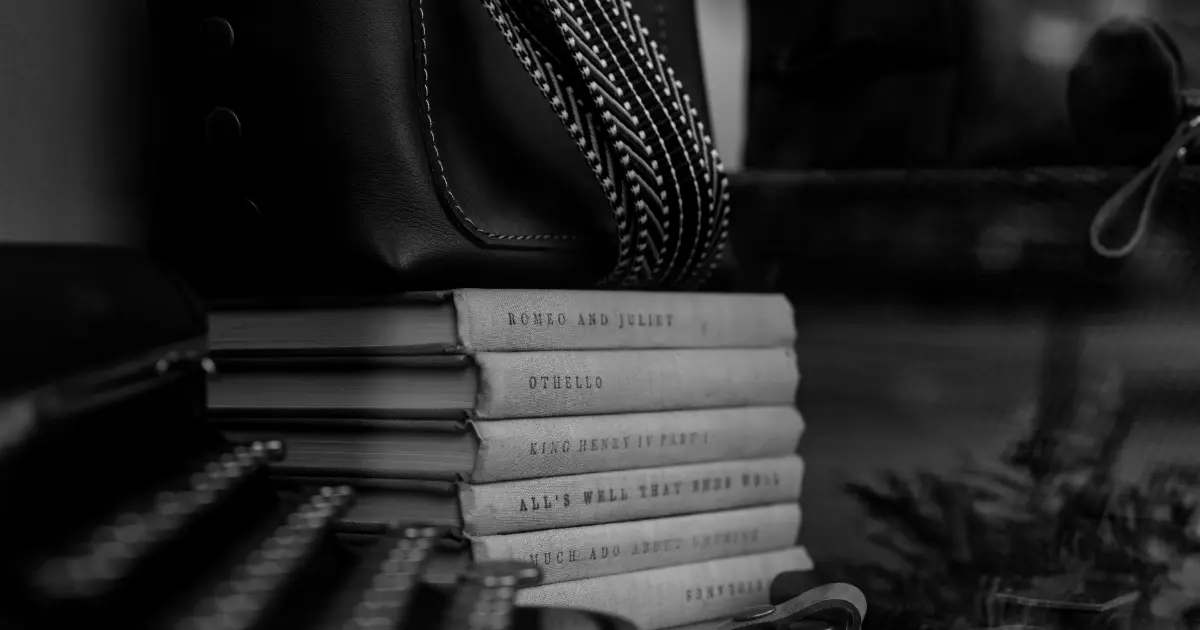


コメント